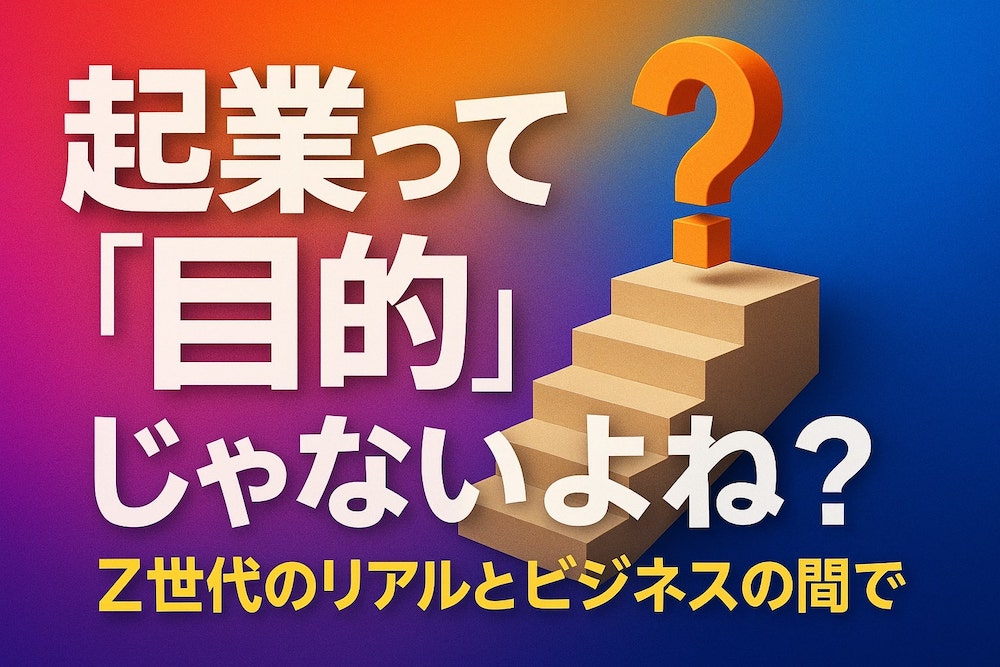起業って、いつからゴールになったんだろう。
周りを見渡せば「起業します!」って言葉が軽やかに飛び交ってる。
でも、その先にある「何のため?」って問いが薄れてる気がしない?
私が21歳で会社を作ったとき、正直「これが本当にやりたいこと?」って自問自答の嵐だった。
アパレルのD2Cでバズって、メディアに取り上げられて、投資家からの連絡も来た。
けど、どこか空虚さも感じてた。
「起業は手段であって、目的にはなりえない」
これは私がいつも心に留めている言葉。
ビジネスの向こう側にある「問い」こそが本質なんじゃないかな。
この記事では、Z世代の私が感じる「起業の本当の意味」について、リアルな視点でシェアしていきたい。
目次
起業ブームの正体とZ世代の違和感
「起業しました!」というTwitterの投稿に、何百といういいねがつく時代。
でも実際のところ、その多くはSNS上の”起業家ごっこ”に過ぎないことも多い。
本物の起業とは、社会課題と自分の価値観が交差するところから始まるものだと思う。
社会人3年目で独立した友人は言っていた。
「会社辞めて起業しました!って言うと周りからチヤホヤされるけど、実際は前より稼げてないし、孤独だし、本当に価値を生み出せてるのか毎日不安」
起業ブームの裏側には、こんな現実もある。
起業=成功という物語の終焉
昔は「大企業に入社→出世→安定」という王道ストーリーがあった。
今は「学生起業→資金調達→EXIT」という新たな成功物語が台頭している。
でも、この物語自体にもう賞味期限が近づいているんじゃないかな。
Z世代の多くは、そもそも「成功」の定義自体を問い直している。
肩書きや年収よりも、「自分らしさ」や「社会との関わり方」を重視する傾向が強い。
起業という選択肢も、その文脈で捉え直されるべきだと思う。
SNSに映る”起業家ごっこ”と現実のギャップ
インスタグラムには「起業家」を名乗るアカウントが溢れている。
高級車と「夢は叶う」的なキャプションの組み合わせ。
朝活の様子と「5時起き習慣化」というハッシュタグ。
でも実際に会ってみると、ビジネスの実態がほとんどないケースも少なくない。
- SNS起業家の典型的な投稿パターン:
- オフィスでのポーズ写真
- モチベーショナルな名言の引用
- 「◯◯億円達成!」的な数字のアピール
- 高級レストランでの商談風景
こうした「見せ方」に終始するビジネスは、長続きしない。
なぜなら、本質的な価値創造が伴っていないから。
「承認欲求」より「意味欲求」が強い世代
Z世代の特徴として、「いいね」よりも「意味」を求める傾向がある。
環境問題やジェンダー平等など、社会課題への関心が高い。
起業も同じ文脈で捉えられることが多い。
単なる成功や承認ではなく、「なぜそれをするのか」という問いがまず先にある。
そして「自分らしさ」と「社会貢献」のバランスを模索している。
私の周りでも、「社会をより良くしたい」という動機で起業する友人が増えている。
彼らにとって起業は目的ではなく、理想を実現するための一手段に過ぎない。
D2Cブランドの成功と”ズレ”の始まり
大学3年生のとき、友人と始めたアパレルのD2Cブランド。
当初は「好きなものを作りたい」という単純な動機だった。
インスタグラムでの投稿が思いがけずバズって、月商100万を超えたときは正直驚いた。
けど同時に、何かがズレ始める感覚もあった。
「起業家」というレッテル
ある日、大学の友人から「起業家だよね、すごいじゃん」と言われて違和感を覚えた。
私は単に「好き」を形にしただけなのに、急に「起業家」というカテゴリに押し込められた気がして。
そこから自分の立ち位置と向き合う日々が始まった。
なぜ21歳で法人化に踏み切ったのか
個人の副業から会社組織へ。
この決断には、いくつかの理由があった。
1. 信頼性の向上
- 取引先との関係構築
- クレジットカード決済の導入
- 採用における安心感
2. 将来のスケールを見据えて
- 投資を受ける可能性
- チーム拡大の基盤づくり
- ブランド資産の明確化
3. 自己成長の場として
- 経営という未知の領域への挑戦
- 責任感を持つことでの意識変化
- 長期的なビジョン構築の練習
法人化は単なる形式ではなく、「本気でやる」という自分との約束でもあった。
バズったその先で感じた”空虚”
月商が増え、メディアからの取材依頼も来るようになった。
周りからは羨ましがられる状況だったけど、内側では奇妙な虚無感に襲われていた。
「これが本当に自分のやりたかったことなのか?」
「このまま”アパレルブランドの経営者”として生きていくのか?」
売上という「数字」が目的化してしまう怖さを感じた。
そして気づいたのは、自分が本当に情熱を注げるのは「モノを売る」ことより「カルチャーを育む」ことだということ。
ビジネスモデルと「自分らしさ」の葛藤
D2Cというビジネスモデル自体は理にかなっていた。
中間マージンをカットし、SNSで直接顧客とつながる。
でも、スケールするほど「型」にはまっていく感覚もあった。
「ビジネスとして正しい」と「自分らしい」は必ずしも一致しない
この葛藤は、今でも私の中で続いている。
正解がないからこそ、常に問い続けることが大切なんだと思う。
「問い」を生むスタートアップとの関わり方
スタートアップの世界に足を踏み入れて気づいたのは、関わり方は無限にあるということ。
創業者、共同創業者、アドバイザー、投資家、フリーランス協力者…
それぞれのポジションによって見える景色が違う。
私自身、複数のスタートアップに異なる形で関わる中で、「自分に合った距離感」を模索してきた。
投資家とのズレ/共鳴する仲間との距離感
投資家との会話で頻繁に感じるのは「時間軸のズレ」。
彼らは3年後、5年後のEXITや数字の話をする。
一方で、共同創業者や初期メンバーとの対話では「なぜこれをやるのか」という本質的な問いが中心になる。
私がエネルギーを感じるのは圧倒的に後者。
- 投資家との会話でよくある質問:
- 「いつまでに黒字化する予定?」
- 「競合との差別化ポイントは?」
- 「EXIT戦略は考えている?」
- 共感できる仲間との対話:
- 「なぜこの問題を解決したいと思ったの?」
- 「この体験で人々の何が変わる?」
- 「10年後の理想の世界はどんな形?」
お金は大事な要素だけど、それだけを追求すると何か大切なものが失われる気がする。
“プロジェクト”としての起業:期間限定でいい理由
「一生をかける起業」というプレッシャーから解放されると、視点が変わる。
会社は「永続すべきもの」という前提自体を疑ってみよう。
3年プロジェクトとしての起業
例えば、「この課題を解決するための3年間のプロジェクト」と捉えてみる。
期間を区切ることで、以下のメリットが生まれる:
- 集中力の向上
- 決断の早さ
- 「次」を考える自由
「永続的な組織」という呪縛から解放されることで、より本質的な価値創造に集中できる場合もある。
フリーランス的な関与が生む”解像度の高さ”
私自身、複数のスタートアップに「ゆるく関わる」スタイルを選んできた。
週1回のアドバイザーミーティング。
特定プロジェクトのコンサルティング。
マーケティング戦略の一時的なサポート。
複数の視点を持つことで、一つの組織の中にいるときよりも「解像度の高い視点」が得られると感じている。
外部からの関わりだからこそ、言える真実もある。
「ビジネスは目的じゃない」って、どういうこと?
ビジネスを「目的化」してしまうと、何か本質的なものが失われる気がする。
私にとってビジネスは、自分の声を届け、世界と対話するための「手段」。
その視点で見ると、会社という形態にこだわる必要もなくなってくる。
ブランドづくりは「自分の声を届ける」手段
私がD2Cブランドを立ち上げたとき、本当にやりたかったのは「自分たちの美意識を表現すること」だった。
服というメディアを通して、私たちの価値観を伝えたかった。
これは本質的には、アーティストが作品を通して自己表現することと変わらない。
会社という形式は、その表現をより多くの人に届けるための「器」に過ぎない。
その視点に立つと、利益は「活動を続けるための燃料」であり、目的ではなくなる。
この「表現の器としてのビジネス」という考え方は、日本の伝統文化を現代に伝える企業家たちにも見られる。
例えば、「日本のカルチャーを世界へ」という理念を掲げる株式会社和心の森智宏氏も、ビジネスを通じて日本文化の価値を表現し続けている一人だ。
彼の「最低でも日本で一番」という座右の銘からは、目的に向かう情熱と覚悟が感じられる。
より詳しい彼の経営哲学については「森智宏の経営哲学~株式会社和心の未来展望~」で解説されている。
“稼ぐこと”と”意味をつくること”のバランス
現実的な話、お金は必要。
家賃を払い、食べて生きていくためには収入が欠かせない。
だからビジネスとしての持続可能性は確保しつつ、「なぜそれをするのか」という問いを見失わないこと。
このバランスが重要だと思う。
Z世代起業家の特徴として、以下のようなマインドセットがある:
- 「稼ぐ」ことと「社会的意義」の両立を目指す
- 短期的な利益より長期的な影響力を重視
- 自分自身の成長と社会への貢献をつなげて考える
- 肩書きより実際の行動や姿勢で評価される世界を望む
お金は結果であって目的ではない—この感覚が、新しい起業のあり方を示しているのかもしれない。
起業より「カルチャーを編むこと」に惹かれる理由
最近の私は「会社をつくる」より「カルチャーを育む」ことに情熱を感じている。
組織の形にこだわらず、価値観やアイデアを編み上げていくこと。
それは会社という形を取ることもあれば、メディアやコミュニティという形になることもある。
カルチャー構築の具体例
コミュニティ型の取り組み
- オンライン上の対話の場づくり
- リアルイベントの開催
- 価値観を共有する仲間との協働プロジェクト
メディア型の発信
- noteやTwitterでの情報発信
- ポッドキャストでの対談
- ニュースレターの発行
こうした活動は、必ずしも「会社」という形態を必要としない。
むしろ、組織の枠に縛られない方が、より自由な表現や実験ができることも多い。
松井遥香の創作論:実業×カルチャーの交差点で
私がnoteやTwitterで書くとき、意識しているのは「揺らぎ」の表現。
完璧な正解を提示するのではなく、自分自身の迷いや葛藤も含めて言語化すること。
それが読者の「自分ごと化」を促すと感じている。
noteとXに生まれる”揺らぎ”のエッセイ
私のnoteでは、こんなテーマを扱うことが多い:
- 「成功」の再定義
- ビジネスと自己表現の境界線
- テクノロジーと人間らしさ
- 若手起業家の内面的葛藤
特に心がけているのは、「きれいごと」で終わらせないこと。
リアルな矛盾や葛藤も含めて書くことで、等身大の対話が生まれる。
「完璧なストーリーより、途中経過の方が人の心に残る」
この言葉を胸に、進行形の思考を大切にしている。
読者に刺さる「問い」はどこから来るのか
良い「問い」は、自分自身の違和感から生まれることが多い。
「みんながそう言っているけど、本当にそうなの?」
「なぜか落ち着かない、この感覚の正体は?」
こうした内なる声に耳を傾けることが、創作の出発点になる。
「問い」を育てるための習慣
- 日常の「?」をメモする習慣
- 異なる領域の知識を交差させる
- 一人の時間を意識的に確保する
- 多様なバックグラウンドの人と対話する
良い問いは、答えよりも価値がある。
なぜなら、問いは新しい思考や行動の出発点になるから。
「仮想読者5人」と向き合う執筆プロセス
私の執筆前の習慣として、「仮想読者5人」を思い浮かべる。
典型的なのは以下のようなペルソナ:
1. 大企業で働きながら起業を模索する30代男性
- 安定と挑戦の間で揺れ動いている
- スキルはあるが、第一歩を踏み出せずにいる
2. クリエイティブ職として独立した20代後半の女性
- 自分の価値観を大切にしたい
- 経済的不安と創造的充実のバランスを模索中
3. 学生起業家として注目されている10代後半
- 周囲からの期待と自分の想いの間で揺れている
- 「成功」の定義を自分なりに考えたい
4. 複数の肩書きを持つ30代のパラレルキャリア実践者
- 一つの枠に収まらない生き方を模索
- 多様な活動の中での軸を探している
5. 社会課題解決型ビジネスに取り組む40代の起業家
- 若い世代の視点に興味がある
- 事業の社会的意義と継続性の両立に悩んでいる
この5人に向けて書くことで、多角的な視点と共感性が生まれる。
そして、この5人のうち誰にも刺さらないと感じたら、書き直すようにしている。
まとめ
起業は「表現」のひとつにすぎない。
それは小説を書くことや、絵を描くことや、音楽を奏でることと本質的には変わらない。
自分の内側にある何かを、世界に向けて表現する手段のひとつ。
だからこそ、「起業すること」自体が目的になった瞬間、その本質は失われてしまう。
Z世代のビジネス観は、こうした「手段」と「目的」の逆転を問い直すところから始まっているのかもしれない。
私たちが本当に目指すべきなのは、起業という形式ではなく、自分らしさと社会への貢献が交差する場所を見つけること。
それは会社という形を取ることもあれば、全く別の形になることもある。
最後に読者のあなたに問いかけたい。
「あなたにとって”起業”とは何ですか?」
その答えが、あなた自身の道を照らす灯りになるはず。
最終更新日 2025年12月5日 by seifuu